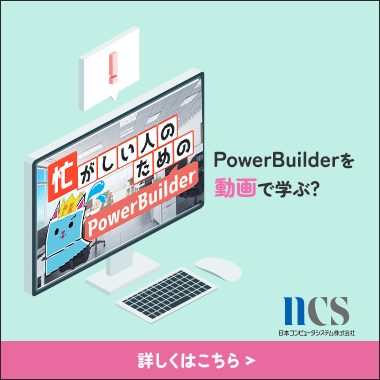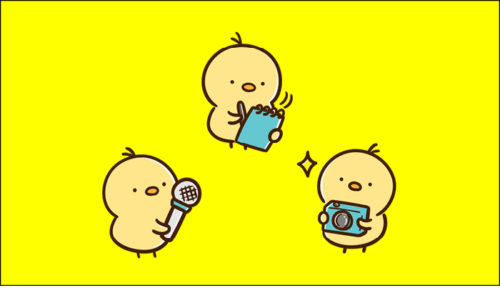PowerBuilder最大の理解者はAIだった

今から5年ほど前のコラム「2025年の崖・・・PowerBuilder営業マンの白昼夢」で、既存ユーザー様から
『PowerBuilderでアプリケーションのモダナイゼーションをしておいて良かった』
『他言語からのリライトはPowerBuilderが最適』
とお褒めの言葉をいただき、更に新規ユーザー様からは
『何故、もっと早くこの情報を教えなかったんだ』
という強いお叱りを受けている自分が…zzz…と書いておりましたが、2025年を迎えるまでも無く、既にこれらはほぼ現実になりました。
5年たっても相変わらず、会社では常に夢みたいなこと(大風呂敷?)を言っております。
最近では当コラムのみならず、社内文書や対外的なメールなども、生成AIを使う機会が増えておりますが、その際に少し羽目を外し、「PowerBuilderとXXX」「PowerBuilderの将来性」などのキーワードでコラムを書かせてみると、妙に納得する文章であったり、このまま掲載しても問題ないのでは?という文章になることばかりです。
これから掲載する内容は、実際に営業現場で見聞きした内容と合致することも多く、PowerBuilderの現在の姿と認識していただければと思います。内容が多少重複もいたしますが、2編引用させていただきます。
1.「PowerBuilder絶好調」というタイトルのコラムをご用意しました。
かつて一世を風靡した開発ツール「PowerBuilder(パワービルダー)」が、今ふたたび静かなブームを巻き起こしています。90年代から2000年代初頭にかけて、業務アプリケーション開発の定番ツールとして多くの企業で採用されてきたPowerBuilder。その後、一時は時代遅れとも言われましたが、近年のアップデートと共に再評価が進んでいます。
その理由の一つは、既存資産の活用が見直されていることです。企業の多くが長年にわたりPowerBuilderで構築された基幹システムを運用しており、これをフルスクラッチで再開発するのはコストもリスクも大きいのが現実。そこで「最新のPowerBuilderで保守・拡張していこう」という流れが生まれているのです。
現行のPowerBuilder(Appeon社が開発を引き継いだバージョン)は、REST API対応やクラウド連携、モダンUIのサポートなど、現代的なニーズにも応える機能が充実しています。また、PowerScriptの高い生産性は健在で、新人エンジニアでも比較的短期間で戦力化できるのが大きな魅力です。
さらに注目すべきは、PowerBuilder 2022 R3以降のロードマップです。Gitとの連携強化、CI/CDのサポートなど、アジャイル開発やDevOpsにも対応しやすい方向へ進化しています。もはや“レガシーなツール”ではなく、“進化を遂げた業務アプリ開発プラットフォーム”と言えるでしょう。
「PowerBuilderなんてもう使われてないでしょ?」と思っているそこのあなた。今こそ、その思い込みをアップデートするタイミングかもしれません。 PowerBuilder、絶好調です。
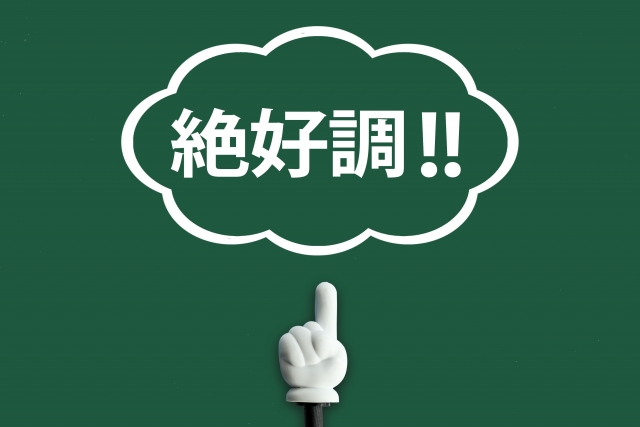
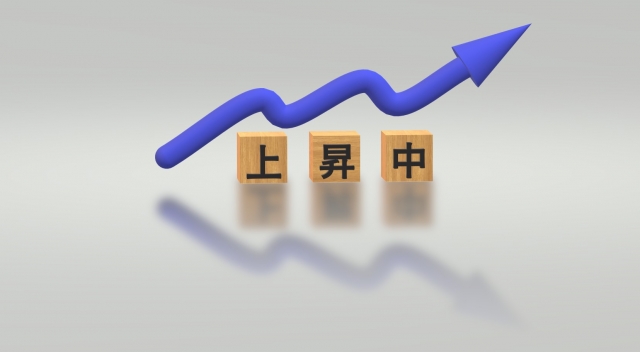
2.「PowerBuilderの時代がやってくる」というタイトルのコラムをご用意しました。
「PowerBuilderって、昔の開発ツールでしょ?」――そう思ったあなた、ちょっと待ってください。確かにPowerBuilderは1990年代から2000年代にかけて、業務アプリケーションの開発現場で広く活躍してきました。ですが、今まさにPowerBuilderが“再び注目される時代”が訪れようとしているのです。
レガシーではなく“進化形”現在のPowerBuilderは、Appeon社が開発を引き継いだことにより、継続的なバージョンアップが行われています。最新バージョンでは、C#との連携強化、クラウド対応、Web APIとの統合、モダンなUI対応など、従来のイメージを覆すような機能が次々と実装されています。 特にPowerBuilder 2022 R3では、Git連携やCI/CDも視野に入れた開発スタイルが実現可能に。つまり、「PowerBuilderは古い」というイメージはもはや過去の話なのです。
DX時代の救世主として今、企業ではDX(デジタルトランスフォーメーション)が求められています。新しい技術を取り入れる一方で、長年使われてきた基幹システムをどうするか、という課題に直面している企業も多いでしょう。
ここで活きるのがPowerBuilderの存在です。既存資産を最大限活用しながら、現代的な技術でアップデートが可能なため、スピーディかつコスト効率の高いDX実現が可能になります。しかも学習コストが低いため、エンジニアの育成もしやすいのが特徴です。
人材ニーズも上昇中実は今、PowerBuilderを扱えるエンジニアの求人が増加傾向にあります。特に中堅〜大手企業を中心に、「PowerBuilderを理解し、保守・拡張できる人材」の需要が再燃しているのです。経験者はもちろん、これから学ぶ若手にもチャンスが広がっており、「PowerBuilderができる人」は今後重宝される存在になるでしょう。
PowerBuilderは過去のものではありません。むしろ、これからの時代にこそ必要とされる“現役ツール”なのです。 静かに、しかし確実に―― PowerBuilderの時代が、やってきます。
如何でしょうか。私が一文字の修正も加えることなく、わずか数秒でこのコラムを書き上げてしまいました。 今までコラム執筆に掛かっていた時間を他の業務に有効活用できるだけでなく、生成AIとのやり取りの中で、新たな「気づき」も得られております。
PowerBuilderの開発現場では既に、ソースコードの自動生成、テストケース・シナリオ作成など多岐に渡り生成AIが活用され始めております。
近い将来、PowerBuilder活用事例で生成AIとのコラボレーションの実態も取り上げてみたいと思います。